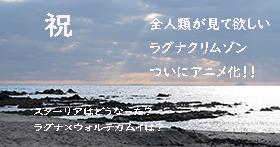一章【橋の下のオーケストラ】
南東北だか北関東だかと言われている、栃木県と茨城県と千葉県北部の東京の玄関口のハブ駅の一つ、北千住駅の改札を抜けると、人の息と笑い声が混じった濁った風が顔に触れた。土埃と排ガスの混じった、どこか懐かしい匂いだった。
午後1時。早春の陽射しはまだ柔らかい。けれど、北千住の空はどこか硬質だ。再開発ビルのガラスに反射した陽光が、冷たく路上を照らす。誰かの人生を焼き尽くすには、まだ温度が足りない。
歩く。駅の西口を出て、ルミネを背にして土手の方へ。
北千住——かつては“治安ワースト”の代名詞だった街が、今では「住みたい街ランキング上位」の顔をしている。
けれどその裏側には、今も生活のざらつきが残っている。朝から飲める路地裏の居酒屋。昼から空き缶を鳴らす老人。無言で並ぶ弁当屋の行列。東京という都市の「終点」であり、「出発点」でもあるこの町には、「音」がある。昔の日本にはあった何とも言えない、感情を持った人間の出す「音」がまだ残っている。珍しい街。
―――
千住新橋。通称「オケ橋」。
今向かっているのは、その橋の下。
かつてこの橋の下は、地元の若者たちから『オケ橋』と呼ばれていた。
理由は単純だった。いつも誰かが音を鳴らしていたからだ。
それはギターの練習だったり、缶を叩いてリズムを刻んだり、ラジカセを持ち込んで踊るものもいた。
だが、音楽を奏でる者たちがいなくなった後も、その「響き」だけはどこかに残っていた。
特に夕方、電車の音が遠くに響き、川のせせらぎが微かに聞こえる時、この橋の下は音を「吸い込む」ような静寂に包まれる。その静けさを破るように、誰かが何かを叩き、鳴らす。
やがて人々は気づいたのだ。
この橋の下では、何を鳴らしても「音楽」になってしまう。
それがリズムであれ、ノイズであれ、吐息であれ——
だから『オーケストラの橋』、略して『オケ橋』。
名付けたのは誰か分からない。
だが、その名だけは生き続けた。
やがて演奏する者たちはいなくなり、橋は都市の中に埋もれていった。
だが音だけは、誰かの中に残っていた。
そして、再び“演奏”が始まったとき、その名が自然と口をついて出た——
「ここ、オケ橋って呼ばれてたんだよ」
日曜の午後、音は不意に始まった。
馬鹿げた話だと思っていた。
そんな。SNSの都市伝説ともただの噂とも思える、誰も確認に行かなそうなネタを調査に行くのが俺の仕事。
世間一般でいうところの、売れないフリーライターだ。
―――
名前は飯田大地。通称ダダ。ジョジョみたいなアダ名は気に入っているが、波紋もスタンドも出せない。吉良にも会ったことない。茨城県の玄関口と呼ばれる町で育った。地元の人間からすると川を越えたらすぐ千葉県であり、実際ほぼ千葉県だと思って暮らしていた。東京の中心地、上野まではわずか40分。そんな微妙な立地にある南東北地方(北関東ではない)の小さな町に、1980年代、俺――飯田大地(通称ダダ)は生まれた。
農協職員の母と消防隊員の父の一人息子として誕生した俺の生まれ方は、少しばかり劇的だったらしい。出産時、へその緒が首に三重に巻きつき、心肺停止状態だった。産声を聞く前に看護師の驚く声が聞こえたと母はよく話していた。最初は息をしていなかったが、背中を強く叩かれて息を吹き返したという。冗談交じりに「テレビと同じ原理で生き返った」と笑いながら話してくれた母の顔は、どこか誇らしげだった。
死にながら生まれてきたのか。生まれながら死のうとしてきたのか。なんだか面白い状態での生誕らしかった。
幼少期は黄疸が強く出たりと健康に不安もあったが、無事に成長し、人より少し感覚が鋭敏になったような気がしていた。それはもしかすると、生まれた時の酸素不足の影響かもしれないと冗談めかして考えるようになった。鋭い感受性のおかげで人の感情を人一倍強く受け止めるようになり、やがてそれが自分の個性として受け入れられるようになった。
そんな好き勝手、感受性強く生きてきた、もちろん独身の45歳。
下北沢駅から坂降りて、王将の手前を左に曲がり、池ノ上駅に向かう途中の教会の向かいにある、2階建ての古びた建物だ。家賃4万5千円の下北沢の木造アパート「小嶺荘」に住んでいる。隙間風は友達みたいなものだ。
このアパートには、夢を見なくなったのか、まだ見れていないのか、そんな、まだ何者でもない人たちが住んでいる。劇団を辞めた役者、バンド解散後のドラマー、離婚して戻ってきた元保育士。俺もその一人だ。
右目だけが黒い伊達メガネ。左目は透明。見える世界と、見たくない世界を分けるフィルターだ。
かつては、戦場カメラマンだった。
―――
きっかけは、 中学の図書館で偶然手に取った、一ノ瀬泰三の『地雷を踏んだらサヨウナラ』だった。タイトルに惹かれた。ドキュメンタリー的エッセイで、戦場ではいつ死ぬか分からないが、それでも前へ進むという強い意志と覚悟を、50文字以上の文字など読んだことなかったのに覚悟を受け取った本だった。極限の中、血と泥と、それでも生きようとする人間の写真、当時、報道されにくい子供や女性の写真が、脳裏に焼きついた。
衝撃だった。まさに、「写真は“記録”ではなく“感情の引き金”となる」引き金引かれて人生決まった。
「誰かが行かなくては伝えられない。誰も行けないなら、自分が行く」——若さの傲慢だったが後悔はない。
ありきたりな高校を卒業し、写真の専門学校に通い、撮り方を覚えたら、早速退学し、飛んだ。
東南アジア、中東、アフリカ。
死と隣り合った土地を、十数年歩き続けた。
そして、アフガニスタンとタジキスタンの国境付近での爆風。
アフガニスタンの山岳地帯で、砲撃に巻き込まれた。
ボロボロで日本に強制送還された、奇跡的に生き延びたが、右目の視神経が損傷しほぼほぼ見えない、色が無くなり、ずっとピンぼけしている状態になった。
世界が変わった。
しかし、不思議なことが起きた、「音」が、見えるようになった。
医者は「PTSDの一種だろう」と言った。
続けて、「しかし、失明し、音が“見える”ようになるとは、脳が視覚の喪失を補うために、聴覚や他の感覚を“視覚的に再構成”して知覚する状態と考えられるかな。実際に一部の盲人が体験している「共感覚的な感覚変換」や、「感覚代行技術」なのかもね」
「はぁ」と適当な相槌をしたが、俺は知っている。
これは、誰かの感情を、音として感じ取る力なんじゃないかと。
例えば、音が見えるようになってから、小鳥のさえずりは淡い黄色で見えたり、車のクラクションは、赤い閃光のように見えたり、近くの人が楽しそうに話していると柔らかい薄い青いリボンが交差した曲線のように見えたりした。
つまり、感情や状況を色や形状、強さで見れるようになったのだ。あまり人には言っていない、言うと馬鹿にされるし、逆に取材されそうで怖くて言ってない。
音が見えるってことは、便利な特殊能力なんかじゃない。最初の頃は興味本位で楽しんでいたが、気づけば、周囲のすべての感情が波のように押し寄せてくることに耐えきれなくなっていた。たとえば、駅のホームで急いでいるサラリーマンの焦りの赤が視界を埋め尽くしたり、家路を急ぐ主婦の漠然とした寂しさが青色の霧のように俺の周りにまとわりついたりする。それはまるで、見知らぬ他人の感情を背負わされて生きているようだった。いつしか、俺はその重みに疲れ、目の前にフィルターをかけることでしか正気を保てなくなっていた。
今は、右目にだけ深い黒色の入ったサングラス型のメガネをかけている。街では少し変わったファッションと見られるが、これはファッションなどではない。右目を覆うレンズは真っ黒で、わずかに青みがかった濃い色彩。俺が持つ、感情を「音」として視覚化してしまう力を抑えるための、ただ一つの方法だ。
精神的に限界が訪れた時、馴染みの眼鏡屋の老人が特殊なレンズを作ってくれた。最初は半信半疑だったが、その右目だけのサングラスをかけると、世界が穏やかな色に戻った。感情は依然として感じ取るが、それはあくまで微かな輪郭としてのみ伝わり、圧倒されることはなくなった。
右目にかけたこの特殊なメガネは、俺にとっては世界と自分を隔てる唯一のフィルターであり、防波堤のような存在になった。街を歩くとき、取材をするとき、そして日常を生きるとき、この片目のサングラスだけが俺を守ってくれる。
だから今日も俺は、この右目だけ黒く染まった視界の中で、静かに生きている。
そんな特技みたいなのを生かせるフリーライターを生業としている。都市伝説、社会の裏側、町の片隅で起きる名もなきドラマを追いかけている。もちろん、それだけでは食べて行くことはできない。

―――
古びたビルの地下、細い階段を降りた先に、ひっそりと構えている。 カフェと骨とう品屋が併設された空間。店の入口は目立たず、看板には「chimera」とだけ筆記体で何かの骨で作られている。 日によって店名の綴りすら変わるように見える。客が入って行くのは見たことあるが、出てくる所は見たことない。誰が買うか分からないボロボロの布や、何語で書いてあるか分からない全三十巻の本や、見たことない色使いのガラス食器、録音テープ、などを扱っている下北沢駅近くのどうやって儲かっているのか分からない、地元の人々も「たまに開いてる不思議な店」としか認識していない「キマイラ堂」でアルバイトをしている。
店主のやっくんのことを説明しようとしても、何から話せばいいのかよくわからない。
たまにふらっと帰ってきて、棚に何か置いていく。使い方も、意味も言わずに。世間のレールから脱線した人。やっくんは、どこで生まれたのか、何をしてたのか、誰も知らない。
店に来た客が聞いても、「忘れた」とか「インドの山奥で茶を淹れてた」とか、適当なことばかり言ってた。
店にはいないけど、誰よりもこの店のことを気にしているし、
誰よりも、俺の顔色に敏感な人だと思う。そういや、やっくんが前に海外から帰ってきた時に言ってた。「世界はね、言葉じゃなくて雑音でできてるよ」って。
どこでどうやって手に入れてくるか分からないが世界中の見たことない雑貨や古本を仕入れてくるというか送ってくる。
ロシアの聞いたこともない詩集、チリの誰かのポスター、ナイジェリアの何かのマニュアル、チベットの即身仏みたいな人形、タイの持ってきちゃいけなさそうな仏像、ジャンルも言語も国もなんの制限もなく送られてくる。
俺の仕事は、それらを開封し、分類し、棚に並べること。値札もやっくんの手書きだ。とてもじゃないが、俺は手が出ないし、買わない値段だ。
カフェスペースは6席ほど。 コーヒーの香りと、アンビエント音楽のような小さな音楽。 アンティークのスピーカーから流れるのは、誰も知らない国の民謡や、名前のないジャズ。
提供されるのはコーヒー一択。 しかもメニューは存在せず、注文すら不要。 カフェスペースに座れば、ダダが勝手にコーヒーを出すシステムだ。一杯500円。現金のみの強気の清算方法だ。
雑貨と古書を売っていて、コーヒーが飲める店は珍しいが、やっくんがそうしてほしいというので、そうしている。気まぐれな日は、焦げ目の強いガーリックトーストが一切れだけ添えられることもある。 それを口にできるのは「今日は大当たりの日」と何しているか分からない常連が言うほどに稀だ。
店に置いてある古本は何がかいてあるか読めるんなら、立ち読み自由。
奇妙なことに、キマイラ堂の売上は年々上がっている。 それも、カフェの収益ではない。 ふと現れる“何かを探す客”が高額で“何か”を買っていくのだ。その客たちは、スーツ姿であったり、民族衣装であったり、顔を隠していたり、顔中ピアスだったりする。 共通しているのは、会話がほとんど交わされないこと。 そして、彼らが手にするのは、棚にある、わけのわからない何かだということ。
レシートも領収書もない。 キャッシュのみ。 買った品の説明を尋ねる者もいない。 ただ、静かに、礼儀正しく支払っていく。
客が来ると、音が歪む時がある。意味のないラジオ波が店内に混じる日があるような日常的違和感を少しだけ感じる時があるが、そんなことは気にしない。
秘密の取引所みたいだ。 けれど、ダダにとってはそれが日常だ。ほぼ毎日、店に立ち、毎日コーヒーを淹れる。
それがダダの居場所。
―――
そして今日も、キマイラ堂で予定を済ませて、小田急線から千代田線に乗り換えて、一時間程電車に揺られて、オケ橋へ向かっている。
10日前から通い続けている。
オカルト系編集者に、「10日間オケ橋に通って、噂は本当か検証してきてくださいよ!」
「面白かったら記事買いますんで!」
「取材費は建て替えでおなしゃす!」
こんな10歳以上も下の編集者に雑にお願いされても、怒らない、断れないのは、仕事をいつも振ってくれる貴重な存在だから。どうやら、昔の俺の写真が好きだったらしい。俺のこと好きなやつはいいやつ。
「初日」誰もいなかった。音もなかった。
「二日目」橋脚の影に、老人がいた。
70代くらいの、痩せた男。服は煤けていて、靴の底がめくれていた。
どうやら、今は缶拾いで生活しているらしい。
―――
二章【ザッザッと掃く老人】
山岸は七十を過ぎていた。
かつては造園業で名を馳せた男だった。江戸時代の回遊式庭園の研究と復元を専門とし、「山岸に任せれば、石が語る」と言われた。新宿御苑の樹木更新計画にも関わり、老舗旅館や文化財の庭園を数多く手掛けてきた。若い頃は黙々と作業する職人タイプで、講釈を垂れる設計者たちとは反りが合わなかったが、技術と審美眼の鋭さでは誰もが一目置いていた。
仕事場では厳しかった。弟子にも容赦なく、「この剪定は木が泣いてるぞ」と叱った。だが、息子には技術を継がせなかった。「好きな道に進めばいい」と言ったのは、他人に厳しかったぶん、家族には自由を与えたいという不器用な優しさだった。
しかし、その息子は家を出たまま、帰ってこなかった。
連絡は途絶え、妻も十年前に病で亡くなった。
退職後は、一人暮らしの団地でテレビもラジオもつけず、新聞と一杯のインスタント味噌汁だけが日々の情報源だった。手入れ道具は倉庫に仕舞いっぱなし。だが、ある日、近所の空き地に咲いていた椿の剪定があまりに酷いのを見て、いてもたってもいられず、勝手に整えてしまった。
その夜、誰も感謝しなかったことに安堵していた。評価も賞賛も、もう欲しくなかった。ただ、「手を動かすこと」が彼にとっての救いだった。
ある日、川沿いを歩いていると、風に舞う枯葉の動きがふと心に引っかかった。葉がひとつ、ゆらりと橋の下へと吸い込まれていく。そのあとを追うように、山岸はふらりと歩いていった。
そこは荒川の橋の下。風が通り抜ける音が、昔の庭の竹垣を鳴らす音に似ていた。
何かが、呼んでいる気がした。
次の日、彼は古いほうきを持ってやってきた。
「掃除をしてやろう」—そう思ったわけではない。ただ、手を動かさずにはいられなかった。
ザッザッ、砂利が石に当たって転がる音。
それは、かつて石庭の「無音の美」を形作るために、何百回と足で踏み固めた音の再現だった。
その音が、懐かしかった。
周囲には何人か人がいたが、誰も話しかけてこなかった。
それがよかった。余計な会話は、葉擦れの音をかき消す。
彼は橋の下の一角を、黙々と掃き続けた。ごみを拾い、落ち葉を集め、わずかな土に手を入れる。
やがて、その場所に“音”が現れた。
紙をめくる音。
自転車のベルの音。
空き缶を蹴る音。
そして、彼のザッザッという掃き音。
それらが、一瞬だけ同じリズムに乗ったように感じた。
山岸は、静かに笑った。
「まだ、奏でられるか」
橋の下で彼が掃除をすることに、誰も文句は言わなかった。
むしろその音があることで、その場所が守られているような空気すらあった。
数週間に一度、若者が来て「この辺、きれいですね」と呟くことがあった。
「風のせいだ」と答えた。
橋の下にいる間だけ、彼は歳を取っていないような気がした。
背筋が伸び、呼吸が深くなり、耳が敏感になった。
風が木をくぐる音。
鳥の羽ばたき。
川面を撫でる音。
それらがすべて、自分を取り囲む音楽のように聞こえた。
ある日、小さな男の子が彼の傍で落ち葉を蹴った。
「カサッ」というその音が、思いのほか澄んでいた。
山岸は、掃除の手を止めて言った。
「いい音だな」
少年は、驚いた顔で彼を見たあと、にっこり笑ってまた落ち葉を蹴った。
そのやりとりが、どこか心の底に熱を残した。
「誰かに褒められるためじゃない」
「誰かと音を共有するために、俺は掃いてるのかもしれないな」
そう、ぼんやりと思った。
家には誰も待っていない。
しかし、橋の下には、音がいる。
音は、嘘をつかない。
今日も山岸は、古いほうきを手に橋の下へ向かう。
ザッザッと、ゆっくり地面を撫でる。
その音は、まるで過去と現在をつなぐ一本の線のように、誰かの心にも届いているのかもしれない。
かつては造園業で名を馳せた男だった。
手入れした庭園は全国誌にも掲載された。
だが、膝を壊し、仕事を後進に譲った途端、家族とも疎遠になった。
「もうあなたの時代じゃない」と言われた。
彼は一人になった。
昼間の町はうるさすぎた。夜の町は静かすぎた。
橋の下だけが、ちょうどよかった。
ザッザッと、ほうきで地面を掃く。
その音が、自分の存在証明のように思えた。
缶拾いも、ただの生活手段ではない。
「まだ俺は拾える」
そう思える瞬間だけが、生きている実感をくれた。
―――
聞こうとすれば音がある
それから毎日、音を出す人を探した。
「三日目」スーツ姿の男が橋の下にいるのだから、サボっているのだろう、書類をペリペリとめくっている。
三章【ペリペリと紙をめくる男】
黒木慶一、五十七歳。元・中堅メーカーの経理部長。
その肩書きが名刺から消えたのは、二年前の冬だった。
会社に入ったのはバブル崩壊直後。氷河期という言葉が定着する直前、大学のゼミの教授の推薦でようやく滑り込んだ。
以来、三十年。
ミスのない帳簿を作ることだけを信条に、黙々と数字と向き合い続けた。
簿記、税制、国際会計基準……時代と共に変わる会計のルールに振り回されながらも、黒木はいつも「正しさ」を手放さなかった。
が、その正しさが裏目に出る日が来た。
数年前、社内のとある部門で、架空経費の処理が常態化していた。
それが「業績維持のための必要悪」だと知った時、黒木は躊躇いなく上司に報告した。
数日後、役員会議に呼ばれた。
結果、地方子会社への異動。
役職も給与も形式上は維持されたが、実質的には“窓際部長”だった。
家族もいた。妻とは結婚して二十五年。子どもは大学生と高校生。
だが、その異動を境に、家の空気も変わった。
「真面目すぎるのよ」妻の口癖になった。
やがて、会社にも家庭にも「黒木慶一」の居場所は曖昧になっていった。
そして、ある朝。
社内の共有机の配置が変わっていた。
自分の名前のある札が、なかった。
人事異動ではない。ただの「整理」だったのだろう。
だが黒木は、その日から会社に足を運ばなくなった。
それでも、家には帰った。だが、行き場を失った感情は空気を重くする。
そんなある日、ふらりと電車に乗って降りた駅が、北千住だった。
大学時代、友人と下町グルメを探して歩いたことがある。
だが、そんな記憶すら今は遠い。
気がつけば足は、荒川の土手に向いていた。
そして橋の下。
風が強く、埃っぽい匂いが漂っていた。
けれど、不思議と落ち着いた。
初日はただ立っていた。
次の日には、鞄から社内資料を取り出して読んだ。
何の意味もなかった。ただ、「ペリペリ」と紙をめくる音が、自分を慰めてくれた。
それが、黒木のリズムだった。
「確認する」ことが、自分の存在を繋ぎとめる行為になっていた。
書類の文字を目で追い、ページをめくる。
それが生活の最後の秩序だった。
橋の下では、誰も彼に話しかけなかった。
誰も、彼の過去を尋ねなかった。
ペリペリという音だけが、責めることなく寄り添ってくれた。
半年が過ぎた頃、黒木は意識して毎週木曜に橋に通うようになった。
「週一」のリズム。
雨の日もあった。風が強すぎて紙が飛んだ日もあった。
けれど、何かに呼ばれるように、足が向いてしまうのだった。
そしてある日、彼は気づいた。
周囲にも、「音」を刻んでいる者がいることに。
チリンとベルを鳴らす若者。
缶を蹴って遊ぶ少年。
箒を引きずる老人。
スマホで頷きながら電話する女性。
その全員が、音を発している。
音は、過去の名刺ではない。
過去の肩書きでもない。
音は、「今ここにいる」ことの証明だった。
そして、黒木もまた、ペリペリという音でそこにいた。
彼はその日初めて、紙をめくる手を止め、耳を澄ませた。
重なっていた。
そして、心のどこかで思った。
橋の下でしか聴けないオーケストラの、ページを、彼は今日も一枚めくる。
―――
「 四日目」主婦が電話の向こうに「うんうん」と頷く。
四章【うんうんと頷く女】
陽子は、この橋の下を「秘密基地」と呼んでいた。
ここに来るたび、自分が少女だった頃の気持ちをほんの少しだけ取り戻せる気がした。
陽子は五十代前半。かつてはジャズシンガーを目指していた。
東京・西荻窪の小さなライブバーで、週末ごとに歌っていた。
バーの名前は「Blue Basket」。地下に降りる狭い階段の先、常連客ばかりの空間で、ピアノとベースの簡素な編成だったが、あの頃の彼女にはそこが世界だった。
「スキャットが陽子さんの声にぴったりだよ」
そう言ってくれたピアニストと恋に落ちた。
でも、夢だけでは食べていけなかった。
彼が音楽留学に旅立つのを見送り、自分は就職。ほどなくして出会った夫と結婚した。
彼は真面目な人だった。子どもが生まれ、生活は安定した。
だが、彼女の中の「歌」が、ゆっくりと小さくなっていった。
育児が落ち着き、パートを始めた。最初は、子どもたちが学校に行っている昼間だけのレジ業務。
けれど、いつのまにか時間も日数も増え、シフトの中心にされていた。
家では、思春期の子どもたちが荒れていた。
長男は口をきかなくなり、長女は「自分でなんでもできる」と突っぱねた。
夫との会話も「今日の夕飯は何?」が中心になった。
その日常に、何度もため息をついた。
ある夜、ふと思い立って、スマホの録音アプリを立ち上げた。
寝静まったリビングで、小さな声で鼻歌を歌った。
「ララルー、ラルル……」
かつて歌っていた曲のフレーズが指先に戻ってくるのに驚いた。
でも、それを保存することができなかった。
(こんなの、誰も聞きたくない)
そう思って、指先で「削除」ボタンを押した。
そんなある日、スーパーの帰り、いつもと違う道を通った。
川沿いの道、風に煽られて買い物袋が揺れる。
目の前に現れたのが、あの橋の下だった。
「まるで映画のワンシーンみたい」思わず笑ってしまった。
誰もいない、埃っぽいコンクリートの空間。
でも、どこか懐かしさを感じた。
それ以来、週に一度、パートの休みにこっそりとここに来るようになった。
夫にも子どもたちにも告げていない。
橋の下では、誰かがひとりごとのように話していた。
陽子は近づかず、少し離れた場所でその声を聞いた。
内容は覚えていない。ただ、その声に「うんうん」と頷いてしまった。
まるで、その人が、自分の心の奥底を代弁してくれているようだった。
次の週、陽子はまたやってきて、今度はベンチに座った。
話していた人物、黒木という男の紙をめくる音が聞こえた。
風の音、川の音、その「ペリペリ」という乾いた音。
自分の中にも、なにかがスーッと流れていった。
陽子は次第に、誰の話にも「うんうん」と頷くようになった。
すると、心の中の「歌」が、また少しだけ、顔を出した。
彼女は録音アプリを立ち上げ、今度は橋の下の音を録った。
川のせせらぎ。
子どもの缶を蹴る音。
ベルの音。
ほうきで掃く音。
その上に、自分の声を重ねてみた。
「ルルル……ルラ、ルラ……」
誰かが拍手したわけではない。
でも、風がやさしく髪を撫でた。
陽子はそれだけで、十分だった。
「ここにいる誰かに、聴いてほしかったんじゃない」
「自分自身に聴かせたかったんだ」
橋の下で、陽子は今日も、そっと頷いている。
自分だけの、誰にも知られない隠れ家。
夫とは数年前から会話が減った。
子どもたちも反抗期に入り、「ママはスーパーのレジだけやってればいいじゃん」と笑う。
彼女はかつて、ジャズシンガーを目指していた。
深夜のジャムセッションで出会った仲間たちも、もうどこか遠くに行ってしまった。
ある日、スマホの録音アプリを使って、こっそり鼻歌を録った。
でも、それを誰にも聞かせることなく削除した。
橋の下に来ると、誰かが話している声が耳に入った。
「うんうん」と頷くこと。それだけで、居場所があるような気がした。
今は、川の音と一緒に、自分の気持ちも流れていくのが分かる。
―――
「五日目」少年が缶を蹴る。カーーンっ
五章【缶をカンカンと蹴る少年】
リクは学校が嫌いだった。
「ちゃんとしなさい」「普通になりなさい」——先生たちはそう言うけれど、その“普通”が何なのか、自分にはわからなかった。
小学3年生のとき、国語の授業中に自分だけ音読のリズムがずれて、みんなに笑われた。
音のリズムに敏感だったリクは、そのズレをわざと変えてみたつもりだった。
だが、「ふざけないで」と怒られた。
中学では美術部に入ったが、いつの間にか無くなっていた。
その代わりに、進学に有利な吹奏楽部を勧められた。
「リズム感があるなら、太鼓でも叩いたら?」
そう言われて、無理やり小太鼓のパートに回された。
でも、合奏は苦手だった。
「テンポが合ってない」「指揮をちゃんと見て」——みんなの音に合わせることは、リクにとって“自分を殺すこと”のように感じられた。
家では、父はほとんど喋らない。
帰宅してもテレビの前でビールを飲み、定時に寝る。
母は几帳面で、毎朝6時に起きて掃除と弁当作りを欠かさなかった。
家中が清潔で、リズムがありすぎるくらい整っていた。
リクは逆に、雑音に救われていた。
スマホの録音アプリを使って、日常の「音」を集めた。
電車のドアの「チン」、自転車のブレーキ音、体育館の床を擦る靴の音、ゴミ収集車の旋律。
その一つひとつを切り取り、自作のアプリで重ね合わせてビートを作るのが、彼の唯一の趣味だった。
友達はいなかった。
でも、イヤホンの中には自分だけの“友達”がいた。
ある日、学校をサボって川沿いを歩いていたとき、偶然、あの橋の下に出た。
風の音が川を滑り、空の下でビルの反響が壁にぶつかって戻ってくる。
そこには何もないのに、たくさんの音がいた。
地面に転がっていた空き缶を見つけて、そっと蹴ってみた。
「カン」と乾いた音が響いた。
それは、自分の声だった。
誰にも遮られない、止められない、自分の意思で出した音。
その音が、橋脚に跳ね返り、川に流れた。
「きれいだ……」
思わずつぶやいてしまった。
それ以来、彼は定期的に橋の下に通うようになった。
放課後、家に帰るふりをして、そのままランドセルを背負ったまま橋の下へ向かう。
空き缶を持参することもあった。
最初はただ蹴っていただけだった。
けれど、ある日、他の誰かもそこにいることに気づいた。
紙をめくる音を立てる男。
何かに頷くだけの女性。
ほうきを引きずる老人。
自転車のベルを鳴らす配達員。
誰も話さなかった。
けれど、誰もリクを責めなかった。
自分の作ったリズムを、イヤホン越しに聴かせたことはなかったが、その場で鳴らす音が、即興の音楽になっているように感じた。
ある日は川の風が強くて、蹴った缶が思わぬ方向に転がった。
それが、配達員のベルの音と偶然重なった。
「今、音楽が始まった」
心のなかでそう思った。
それからというもの、リクは“今日の音”を意識するようになった。
缶の素材、空気の湿度、風向きで、音の高さが微妙に変わる。
「カン」「コン」「キン」その違いは、リクにとっては明確だった。
誰も褒めてくれなくていい。
ただ、自分の存在が、この音の中にある気がした。
家庭でも学校でも“空気を読む”ことに疲れていた。
でも、ここでは空気が音になって応えてくれた。
リクは、音の中に「言葉のかわり」を見つけていた。
一度だけ、母に「川で遊んでたの?」と聞かれたことがある。
そのとき彼は、嘘をつけなかった。
「うん……橋の下で、音を探してた」
母は、少しだけ黙ってから「気をつけてね」と言った。
それだけでよかった。
リクは今も、缶をひとつだけポケットに入れて橋へ向かう。
ランドセルは軽い。
でも、彼の中には、無数の“音”が詰まっている。
今日も、「カンカンカン」と蹴りながら、彼は音楽を奏でている。
誰にも聴かれなくていい。
ただ、それが自分の声だから。
―――
「六日目」誰も前にいないのに、配達員が自転車のベルを鳴らす。チリンっ
六章【チリンチリンと鳴らす配達員】
ジュンの自転車は、兄の形見だ。
赤錆が浮き出したフレーム、擦り切れたサドル、後輪に少しだけ癖のある回転。
けれど彼にとって、それは世界で一番スムーズな自転車だった。
兄の名前は航太(こうた)。
七つ年上で、いつも面倒を見てくれた。
中学の頃は、ジュンをいじめていた上級生に黙って殴りかかったこともある。
けれど航太は、家では一切それを言わなかった。
「黙ってりゃ、バレないこともあるだろ」
その言葉が、ジュンのなかでひとつの指針になった。
航太はバイク便の仕事をしていた。
雨の日も雪の日も、封筒を抱えて東京の街を縦横無尽に走った。
親は離婚し、母と三人暮らし。兄が働かなければ、家計はもたなかった。
「お前は勉強だけしてろよ」
そう言って、ジュンの高校入試の前日も、兄は夜遅くに帰ってきた。
そのままシャワーも浴びず、コタツで眠った兄の寝息を聞きながら、ジュンは自分の無力さを痛感した。
兄が倒れたのは、ジュンが高校二年の春だった。
配達先のビルで倒れ、そのまま帰らなかった。
診断書には「過労性心不全」とあった。
けれど、どれだけの疲れや孤独や苛立ちが、その言葉の裏にあったのか。
ジュンには、わからなかった。
だからこそ、葬式の後、彼は兄の自転車を持ち出して、同じ仕事を始めた。
家族に黙って、履歴書を書き、バイク便の代行業務を請け負う会社に登録した。
最初は怒られた。
「この荷物の重要性がわかってない」「言葉遣いがなってない」
でも、ジュンは辞めなかった。
兄がどんな目をしていたのか、どんな音を聞いていたのか、知りたかった。
彼はヘルメットを深くかぶり、街に出た。
街は騒音に満ちていた。
車のクラクション、スマホの着信音、店のアナウンス。
だがジュンは、細かい音を聞くようになった。
子どもの笑い声、風で揺れる旗の擦れる音、信号が青になるときの微かな電子音。
それらが、どこか心を落ち着かせた。
ある日、配達の途中、時間調整のために立ち寄ったのが、あの橋の下だった。
荒川の風が抜ける音。
誰もいないのに、何かが「いる」ような気配。
ジュンは、兄の名前を呼んでみた。
応答はなかった。
だが、自転車のベルを「チリン」と鳴らすと、どこかで振り返ったような気がした。
それ以来、彼は配達の合間に、橋の下に立ち寄るようになった。
音を鳴らすためではない。
けれど、鳴らさずにはいられなかった。
「チリンチリン」
その音は、街ではノイズだ。
けれど、ここでは挨拶だった。
橋の下には、いろんな人がいた。
紙をめくるスーツの男。
頷くだけの女性。
缶を蹴る少年。
掃き掃除をする老人。
誰も、ジュンに話しかけなかった。
だが、自転車のベルが鳴ると、誰かが必ず一度だけ顔を上げた。
その一瞬が、嬉しかった。
ジュンはいつしか、配達の荷物を届けた後、橋の下で深呼吸することが習慣になった。
街の喧騒から切り離された、もうひとつの街のような場所。
兄のいた世界に少しだけ近づいたような、そんな感覚。
ある日、風が強い日に、自転車のベルが自然に「チリン」と鳴った。
それが合図のように、少年が缶を蹴り、女性が小さく頷いた。
「今、音楽が始まったな」
ジュンは思った。
誰も指揮していない、誰も演奏しているつもりのない、オーケストラ。
けれど、それは確かに「鳴っていた」。
ジュンはそっと自転車を停め、橋の柱に背を預けた。
兄がここにいたかどうかは分からない。
けれど、音が答えてくれる。
「今日も、お前は走ってたな」そんな風に。
そして彼は、もう一度だけ、ベルを鳴らした。
「チリンチリン」
それが、自分なりの祈りだった。
―――
七章「騒音の旋律」
「七日目」二日目の老人がほうきを動かす。ザッザッザッザッ。
どれも、生活の“雑音”だった。
また、SNSの噂か。
「八日目」「九日目」橋の上の車のクラクションが今日は多い。
橋の下では微かな異音を耳にしていた。まるで古いラジオが混線しているような、聞き慣れない言語の囁きが、風に混じって漂っていた。しかし、気のせいだろうと振り払っていた。
「十日目」午後2時30分。風が川面を舐め、排ガスを巻き込んで運んできた。オケ橋に近づくにつれ、いつもと違う音が響いている。
バイオリンの音だ。
橋脚の奥。壁に向かって座ってバイオリンを弾いている。
黒ずんだコート。猫背。フードをかぶっていて顔が見えない。
びっくりする程、下手くそだ。
弓の運びは拙く、音程も不安定。
けれど、なんだか一生懸命で心に届く音だった。
しかし、あれはバイオリンなのか?見たこともない素材。木のような、骨のような。
しばらく聞いていたくなる音だった。一生懸命で、どこか淋しげで。
他にも聞いている人がいるのは分かっていたが、彼の奏でる音を聞いていたかったので、座って聞いていた。
不思議だ、橋の上では、トラック
やバイクが騒音を出して走っているのに、音が重なり、騒音との旋律になっている。
その旋律に
紙の音。ペリペリ。
相槌。うんうん。
缶の音。カンカンカン。
ベルの音。チリンチリン。
ほうきの音。ザッザッ。
周りを見渡すと、二日目から音を出してきていた老人や主婦、小学生たちが、偶然にも全員いる。そして、音を出している。
音は、叫びだ。
そして叫びは、音楽になる。
どれも、孤独が刻むリズムだった。
そして、その孤独の音が、橋の下で共鳴したとき
音は重なり、ひとつの旋律となった。
バイオリンの拙い旋律が響き始めた。周囲の騒音や雑音が不思議と溶け込み、リズムを刻み始める。紙をめくる音はパーカッションのようにリズミカルに刻まれ、「うんうん」という女性の相槌は柔らかなハミングとなり、少年の蹴る缶の音が軽快なドラムとなって跳ねた。配達員のベルがきらめくように旋律を彩り、老人の箒が地面を擦る音が低く深いベースラインを描く。これらが重なり合い、孤独な個人の叫びが見事に調和した音楽へと変貌した。その瞬間、鳥肌が立つほど美しい旋律が橋の下を満たした。
橋の下の生活音が、奇跡の旋律になった。
だが、彼らの誰も、その奇跡に気づいていない。
唯一、それを見る目を持ったのが右目の見えないダダだけだ。
なんだなんだどうなっている。
右目が激しく痛んだ。閉じているはずの瞼を鋭利な光が突き抜けるような、激しい熱と鋭い痛みが同時に襲いかかる。視神経が溶けるような錯覚すら覚えた。見えないはずなのに眩しさが押し寄せ、俺は顔をしかめて右目を強く覆った。
(なんかすんごいの来る)
振り返ったバイオリン弾き。どす黒い顔色。顔色は緑色?しかし、困惑の表情。
「ما الذي מהעושהδιάολο بאתה حق الجΤι στολο;حيم؟」
何語だ?世界中に結構行ったが聞いたことない言語だ。
痛い、目が痛い。
(なんか来た)
大きなトラックが橋の上を通った瞬間、突然、周囲の空気が震え出した。橋の壁に裂け目が生じ、その隙間から淡い光がゆっくりと漏れ始める。光は水面に垂らされたインクのように、ゆらりと空間を侵食し、広がっていった。裂け目から覗くのは、色彩が渦巻く異様で美しい風景――見たこともない植物が揺れ、見たこともない生き物が飛び交う、不思議な世界が微かに垣間見えた。俺の右目はその光景に焼けつくように痛みを感じ、感覚が研ぎ澄まされると同時に、その向こう側の世界が呼吸する音までもが鮮明に響いてきた。扉の向こうでは音楽が流れ、あちらの世界の鼓動そのものが、ここまで届いていた。
光が彼を包んだ。振り返り笑って、そして、消えた。
周りの誰も、異変に気づいていない。自分に夢中だ。
そして、主婦はスマホを仕舞い、配達員は次の注文を確認し、少年は缶を拾い、スーツ男は鞄を閉じた。
静かに、散っていった。
日常へ戻るように。
右目だけが知っていた。
バイオリンを弾いていた彼なのか彼女なのかは、自分の世界に帰ったのだ。
振り返った顔はゴブリンのような異様な姿だったが、不思議とどこか親しみがあった。悪意は感じない。それよりも、何故か懐かしさすら覚えた。
―――
「まさかの異世界落ちかよ……」
それが、俺にできた唯一の突っ込みだった。
不思議なんて日常茶飯事だし、慣れたもんだ。
生きるか死ぬかの現場を知ってる身からすれば、異世界のひとつやふたつ、どうってことはない。
…と、自分に言い聞かせながら、ひと呼吸だけ、目を閉じた。
―――
目が痛いが記事にするために、ノートに書き留める。
また、信じてもらえなさそうだが、現実に起こったのだから書き留めよう。
―――
【《真相!!橋の下のオーケストラ。音の共鳴が、扉を開けた》東京都足立区・北千住にある荒川の千住新橋、通称『オケ橋』。 ここ数年、SNSや匿名掲示板で静かに噂が広がっている。
『橋の下から、音楽が聞こえる』 『その音を聞いた者の人生が変わる』
最初は笑い飛ばしたが、取材のために訪れたその場所で、私は確かに「音」の奇跡を目撃した。
昼下がり。雑音と思われたそれぞれの音――紙をめくる音、相槌を打つ音、空き缶を蹴る音、自転車のベル、ほうきで掃く音が、突如バイオリンの音色に導かれ、美しい旋律を生み出したのだ。
その共鳴の頂点で、私は『世界の境界』が開く瞬間を見た。 フードを被った謎のバイオリン奏者は異国の言語で何かをつぶやき、光に包まれ消えた。
誰も気づかないその出来事を、なぜか私だけが見ることができた。 あれは、孤独な魂が奏でた奇跡なのか、それとも異世界からの来訪者が残したメッセージだったのか。
真実はまだ霧の中だ。 しかし、私は断言する。
オケ橋には「見えない扉」が存在する。 そしてその鍵は、私たちが日々無意識に刻む、小さな孤独の音にあるのだと。
あなたも耳を澄ましてみてほしい。 そこに、新たな世界が待っているかもしれない。】
―――
夢中で先程起こった事実を書き殴り、そろそろ日も暮れて文字も見えなくなりそうだったので、残りはキマイラ堂で書こうと腰をあげた。
いつの間にか右目の痛みは、消えていた。
日が暮れていく北千住の街をゆっくりと歩いた。冷たい風が頬を撫で、夕焼けが空を深く染めていた。振り返ると、橋の下での奇妙な出来事はすでに現実離れして感じられたが、右目に残る微かな痛みが、それが確かに起こった証拠のようだった。
駅前の天七で一杯だけ飲み、電車に揺られて下北沢へ帰る。店の窓に映る自分の顔には疲れと僅かな興奮が入り混じり、俺は静かに微笑んだ。
「信じてもらえない記事か。でもそれも悪くないな」
俺はそう呟きながら、帰路についた。
八章『音の底にあるもの』
夜のキマイラ堂は、昼間とはまるで違う場所のように静かだった。コーヒーの香りすら、今夜はどこか遠慮がちで、壁にかけられた古いモノクロ写真だけが、過去を黙って見つめている。
ダダはカウンターの奥、いつもやっくんが座る場所に腰を下ろしていた。やっくん本人はここにはいない。けれど、なぜか、椅子には微かに温もりが残っているような気がした。
ポケットから古びたメモ帳を取り出す。薄くなった紙の中に、これまで出会った客たちの何気ない言葉や落書きのような会話の断片が記されていた。
「音は聴こえるものじゃなく、浮かび上がるものだよ」
「人は誰でも、自分だけの周波数を持っている」
「わからないことがあるなら、わからないまま抱えていけばいいんだ」
「酒は飲んでも飲まれるな」
断片的な言葉が、不意にひとつの線で結ばれていく。けれど、完全に輪になるわけではない。まだ、空白はある。
埋めきらなくてもいいのかもしれない。
彼はそっと、扉の内側に掛けられていた「営業中」の札を裏返した。「準備中」という字面が、今夜の自分にはやけにしっくりくる。
カウンター越しに見える店内には、いつの間にか静かな音が満ちていた。時計の針の音、コーヒーマシンの吐息、冷蔵庫の低い唸り。どれもが、街の外音と重なり、目に見えない旋律を作り出している。
「あの人は、なぜ俺にこの店を任せたんだろう」
それはずっと答えの出ない問いだった。でも今、少しだけ、その意味に手が届きかけている気がする。
店内に置かれたアンプのスイッチを入れ、カセットテープを回す。音が流れる。昔のジャズだった。擦れたトランペットの音が、まるで声を持ったように空間を撫でていく。
その音に耳を預けながら、ダダは思った。
「もしかすると、世界は俺が思ってるより、ずっと優しく、ずっと曖昧なんじゃないか」
彼の視線は壁の一角にある、一枚の小さな写真に止まった。それは、やっくんが初めて店を開いたころの写真だった。隣に、見慣れない若者が写っている。顔はぼやけているが、どこか自分に似ている気がした。
胸の奥に、小さな震えが広がる。
すべての謎を解こうとしなくていい。すべてを語ろうとしなくていい。ただ、立ち止まらずに「次へ」進めばいいのだ。
店のドアが、誰も触れていないのに、カタリと小さく鳴った。
気のせいかもしれない。けれど、なぜか――ほんのわずかに、空気が入れ替わったような気がした。
あとがき
この物語には、いくつかの謎が登場しますが、どれも「解かれること」を前提にしていません。
ただ、“感じたこと”だけが、本当にあったことだと、主人公と一緒に信じていただけたら幸いです。